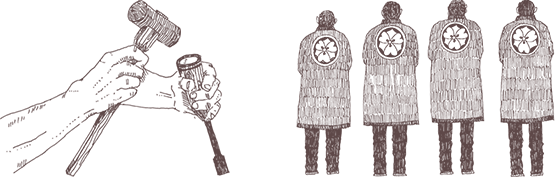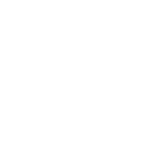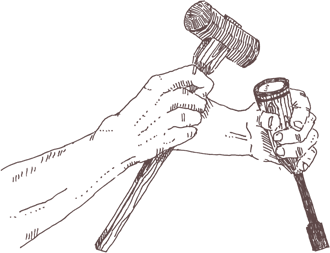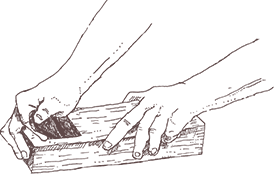タケと竹に違いがあるのをご存知でしょうか? タケは、生命を保持している状態、つまり竹林のように土から生えている状態を植物として「タケ」と呼び、その土から出てきたばかりのものを「タケノコ(筍)」と呼びます。また、伐採されて利用される段階のことを「竹」と漢字で表現することで、発生から利用までの各過程における状態を視覚の上から理解しやすくされているのがわかります。 竹は、その美しさと実用性で古くから親しまれてきた植物です。 日本文化や建築の中でも、竹は特別な存在として多くの場面で利用されてきました。そのしなやかな形状と強さ、そして環境へのやさしさから、近年では再び注目を集めています。 このブログでは、「竹」について、建築を交えてご紹介させて頂きます。 タケの基本情報 タケはイネ科の植物で、草の一種です。 世界中に1500種類以上が存在し、特にアジア、南アメリカ、アフリカで多く見られます。 タケは成長速度が非常に早く、1日に1メートル以上伸びることもあるため、持続可能な資源として注目されています。また、竹林はCO2を吸収し、大気の浄化にも寄与しています。 タケの面白い一説 日本最初の歴史書と言われている古事記によると、「イザナギノミコトが追いかけてくる魔女達に自分が使っていた湯津妻間櫛(ゆつつまぐし)を投げつけたところ、タケノコが生えてきたため、魔女らがそれを食べている間に逃げた」とあり、日本書紀には「コノハナサクヤヒメが皇子を出産された際に臍の緒を竹刀で切り、これを土に挿しておいたところサカサダケが生えてきた」という神代時代の記事が残っているそうです。 竹の歴史 竹の利用は古代にさかのぼります。 中国では紀元前5000年頃から竹が使われており、紙の製造や楽器、弓矢、槍などの武器に広く使用されてきました。 また、竹簡(たけかん)と呼ばれる竹製の書物は、文字記録の初期形態として使用されていました。 [caption id="attachment_7836" align="alignnone" width="640"] Chinese traditional bamboo slips. This is one of the main media for literacy in early China.Chinese characters were inscribed on a long, narrow strips of bamboo each, and many slips were bound together in sequence with thread[/caption] 日本では縄文時代から竹が使用されており、釣り竿や籠、農具など、実生活に密着したアイテムが多く作られていました。 奈良時代になると、竹は宗教的儀式にも使われ、神社や寺院の装飾にも多用されました。 有名な『竹取物語』は竹を題材にした日本最古の物語であり、竹が文化的にも重要な位置を占めていたことがわかります。 竹と建築 竹は建築材料としても非常に優れています。 その軽さと強度、そしてしなやかさから、伝統的な建築物や現代のエコ建築まで幅広く使用されています。 日本の竹建築 日本では庭園や茶室に見られる竹垣(たけがき)は、日本の伝統美を象徴しています。 竹を縦横に組み合わせた垣根は、視覚的な美しさだけでなく風通しの良さを提供します。また、茅葺(かやぶき)屋根の骨組みに竹が使われることもあり、その柔軟性と耐久性が活かされています。 竹の網代 日本の伝統的な建築技法の一つで、竹を割いて縦横に編み込んで格子状の模様を作り、和室や茶室、民家などに用いられます。この技法は、竹の軽さと丈夫さ、また湿度調整機能を活かし、自然な質感と温かみを空間に与えます。 竹の網代模様は幾何学的な美しさがあり、落ち着いた雰囲気を作り出すため、特に茶室や古民家で好まれています。 仕上げに漆や木材を使うこともあり、見た目の高級感や耐久性が増すことも特徴です。 東南アジアの竹建築 インドネシアのバリ島では、竹を使ったモダン建築が注目されています。有名な例として、「グリーンスクール」と呼ばれる建築物があります。校舎の全体が竹で作られており、地元の素材を活かしたサステナブルデザインの象徴とされています。 [caption id="attachment_7838" align="alignnone" width="633"] BALI, INDONESIA - FEBRUARY 2012: Classroom interiors at Green School on Februray 27, 2012 in Bali, Indonesia. The school is known for promoting eco-friendly concepts to its students.[/caption] 現代建築での応用 ベトナムの建築家ヴォ・チョン・ギアによる竹建築は、軽量でありながら頑丈なドーム構造が特徴です。 これらの建築はエネルギー効率が高く、自然環境との調和を目指しています。 竹の文化的な意味 日本では、竹は古くから生活や文化に深く根付いています。たとえば、神道のしめ縄に使われる竹は、神聖なものとされ、邪気を払うと信じられています。また、茶道具として使われる竹の茶杓(ちゃしゃく)や茶筅(ちゃせん)は、茶道の精神性を象徴する重要な道具です。 竹林もまた特別な意味を持ちます。京都の嵐山にある竹林の小径(こみち)は、日本を代表する観光地であり、その幻想的な雰囲気が国内外の人々を魅了しています。竹林はまた、映画や文学においても静けさや神秘を表現する舞台として用いられることが多いです。 竹の実用性 竹は軽量でありながら強度が高く、建築資材や家具、食器、楽器など、さまざまな用途で活用されています。 家具 竹を使った椅子やテーブルは、軽くて持ち運びがしやすい上に耐久性に優れています。 楽器 篠笛(しのぶえ)や尺八(しゃくはち)などの日本の伝統楽器は、竹の独特な音色を活かして作られています。 食品 竹の子(たけのこ)は春の味覚として親しまれ、食卓を彩る食材の一つです。 さらに、竹炭や竹酢液は消臭効果や抗菌効果があり、エアフィルターやスキンケア製品に応用されています。 環境への貢献 竹は持続可能な資源であり、環境保全に大きく貢献します。 成長が早いため、伐採後の再生が早く、木材の代替品として利用することで森林伐採を減少させる効果があります。 また、竹の根は地中深く張り巡らされており、土壌の浸食を防ぐ役割を果たします。さらに、竹製品は自然に分解されるため、プラスチック製品の代替として注目されています。 おわりに 竹はその魅力的な外見と多様な利用法で、私たちの生活に多くの恩恵をもたらしています。竹細工の篭やランプシェード、カトラリーや日用品など持続可能な未来を目指す上で、竹の重要性はますます高まっています。 歴史や建築における竹の役割を知ることで、その価値をさらに深く理解することができます。ぜひ、この機会に竹についてもっと知り、その素晴らしさを感じてみてはいかがでしょうか。 参考文献:「日本の原点シリーズ」新建新聞社 丸晴のブログはこちら https://www.marusei-j.co.jp/土間ってどんな種類があるの?一般的なのはコン/ 丸晴工務店のYouTubeはこちら https://youtu.be/OzHdDn91