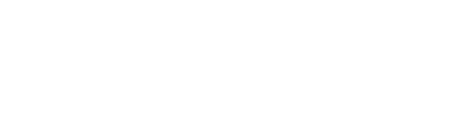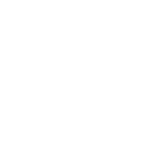知っていますか?大谷石と深岩石のこと。
2024年12月28日石材は、建築やインテリア、庭園など幅広い分野で利用されており、その特徴や用途によって選ばれます。
簡単にいうと、柔らかさと暖かみを持つ大谷石、そして重厚で耐久性に優れた深岩石。
この記事では、日本の代表的な石材である「大谷石」と「深岩石」の違いについて解説します。
目次
大谷石(おおやいし)
大谷石(おおやいし)は、栃木県宇都宮市周辺で産出される火山灰由来の凝灰岩で、以下のような建築的特性を持っています。
歴史
一躍大谷石を全国に広める大きな役割を果たしたのは、なんと いっても大正時代に建造された、旧帝国ホテルです。
このホテルは後の関東大震災にも焼け残り、その優美さは設計者 フランク・ロイド・ライト氏の傑作とい われました。
使用された大谷石とスクラッチ練瓦とテラコッタと大谷石の彫刻の絶妙な組み合わせは、大谷石の特徴である素朴で 柔らかく温かみのある質感が遺憾なく発揮されブームとなりました。
特に昭和初期の教会堂建築などに数多く用いられ、宇都宮市内にある国登録有形文化財、設計者マックス・ヒンデル氏のカトリック松が峰教会や設計者上林敬吉氏の日本聖公会宇都宮聖ヨハネ教会等は大谷石建造物の代表作であります。

特徴
緑色がかった色合いで、ミソと呼ばれる茶色の斑点が特徴です。このミソは粘土鉱物で、長い年月を経て抜け落ちることがあります。
古くから石倉や石塀に使われてきた大谷石。内装材・オブジェ等にも様々な加工品としても広く用いられ、大谷石の控えめな地色、素朴であたたかみを感じさせる、独特の風合いが古くから愛されています。

採掘場所
栃木県宇都宮市大谷町付近
硬度
大谷石の硬度は約3.5から4.0の範囲です。これはモース硬度で測定されるもので、比較的柔らかい石材に分類されます。
調温・調湿効果
天然ゼオライトの多孔質構造は、温度・湿度を一定に保つ調温・調湿効果があります。大谷石の空間は、夏は涼しく、冬は暖かく快適です。
用途
古くから建築材料として使用され、特に蔵や石塀、石段などに利用されています。
火に強く、煮炊きをするかまどをはじめ、様々な形で使用されてきました。最近では大谷石のピザ窯も人気です。遠赤外線がおいしさを増幅させます。
深岩石(ふかいわいし)
深岩石(ふかいわいし)は、岐阜県周辺で産出される花崗岩で、建築において以下のような特性が評価されています。
歴史
深岩石は、古代から日本の建築や工芸に利用されてきました。
特に、古墳時代には石棺や石室の材料として使用され、中世には城や寺院の建築にも使われました。
中世の深岩石を使った代表的な建物としては、ゴシック建築の大聖堂が挙げられます。
ゴシック建築は、12世紀から16世紀にかけてヨーロッパで発展した建築様式で、特に教会や大聖堂に多く見られます。
ゴシック建築の代表的なものは、以下のものがあります。
・ノートルダム大聖堂(フランス)
・シャルトル大聖堂(フランス)
・ケルン大聖堂(ドイツ)
・ミラノ大聖堂(イタリア)

採掘場所
岐阜県およびその周辺
硬度
深岩石の硬度は約4.0から5.0の範囲です。大谷石よりも若干硬く、耐久性が高いです。
調温・調湿効果
吸水率: 吸水率14.1%と低く、水や温度差による風化に強いです。
用途
壁材や床材、装飾品として利用され、特に耐久性と断熱性が求められる場所に適しています。
現代の利用例
最近では、深岩石を使ったモダンな建築やインテリアデザインが注目されています。
例えば、住宅の外壁や庭の敷石、さらにはカフェやレストランの内装にも取り入れられています。
加工

参考資料:大谷石産業株式会社https://ooyaishisangyo.com/material/fukaiwa/
大谷石と深岩石の建築的比較
大谷石と深岩石はどちらも栃木県で採掘される岩ですが、いくつかの重要な違いがあります。
| 特徴 | 大谷石 | 深岩石 |
|---|---|---|
| 主な産地 | 栃木県宇都宮市 | 岐阜県およびその周辺 |
| 種類 | 凝灰岩 | 花崗岩 |
| 加工のしやすさ | 非常に加工しやすい | 加工はやや難しい |
| 耐久性 | 一般的 | 非常に高い |
| 建築での用途 | 外壁材、内装材、石蔵 | 基礎材、外壁材、モニュメント |
建築と石材の未来
大谷石と深岩石は、それぞれの特性を活かし、日本建築の伝統と革新を支えています。柔らかさと暖かみを持つ大谷石、そして重厚で耐久性に優れた深岩石。それぞれの魅力を活用することで、新たな建築デザインの可能性が広がっています。
これらの石材を利用した建築物は、単なる構造物を超えて、地域文化や歴史を伝える象徴的な存在となるでしょう。もしこれらの石材を実際に見たり触れたりしたい場合は、大谷資料館や地域の建築現場を訪れてみてはいかがでしょうか。
丸晴のYouTubeはこちら
丸晴の施工事例はこちら