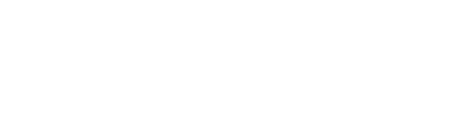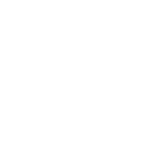イチョウは針葉樹?広葉樹?—分類学から見る“生きた化石”の正体
2025年4月8日
秋の黄葉の象徴とも言えるイチョウ(Ginkgo biloba)。その扇形の葉は広葉樹的な印象を与えますが、植物学的には一筋縄ではいかない存在です。本記事では、「イチョウは針葉樹か、広葉樹か?」という問いを、植物分類学・系統学・形態学の観点から掘り下げます。
目次
広葉樹と針葉樹:分類の誤解
まず一般的な誤解を整理しましょう。
日常的には、
-
広葉樹(broadleaf trees)=葉が広くて平たい
-
針葉樹(coniferous trees)=葉が細くて針状
と形態(見た目)で区別されますが、植物分類学においてはこれはあくまで表層的な区別です。
実際には、以下のように分類されます。
| 分類 | 主な植物群 | 特徴 |
|---|---|---|
| 被子植物(Angiosperms) | 桜、楓、椿など | 種子が子房に包まれている(果実ができる) |
| 裸子植物(Gymnosperms) | マツ、スギ、イチョウなど | 種子がむき出しで果実ができない |
つまり、広葉/針葉は形態的な便宜的表現にすぎず、分類学的には被子植物か裸子植物かが重要になります。
イチョウの正体:裸子植物かつイチョウ門
イチョウ(Ginkgo biloba)は裸子植物に分類されますが、さらに特筆すべきは、それが独立した分類群(イチョウ門 Ginkgophyta)に属している点です。
-
現存する唯一の種
-
およそ2億年以上前の中生代から形を変えずに生き残っている
-
他の裸子植物(マツ類、ソテツ類など)とは系統的に異なる
このためイチョウは「生きた化石(living fossil)」と呼ばれるのです。
系統樹の位置づけ
植物の系統樹におけるイチョウの位置は以下のようになります。
種子植物
├── 被子植物(Angiosperms)
└── 裸子植物(Gymnosperms)
├── マツ門(Pinophyta)
├── ソテツ門(Cycadophyta)
├── グネツム門(Gnetophyta)
└── イチョウ門(Ginkgophyta)←ここ!
イチョウは“針葉樹”なのか?
分類学的には、針葉樹という言葉はマツ科やスギ科など、狭義の「針葉植物(Pinophyta)」に対して使われます。イチョウはこれに含まれないため、
正確にはイチョウは“針葉樹ではない”
という答えになります。
しかし、日本語で「針葉樹」と言うときはしばしば「裸子植物全体」を指す場合もあり、その文脈では「広葉樹ではなく針葉樹に分類される」という表現も使われます。
つまり、
-
形態的には広葉樹的
-
系統的には裸子植物
-
分類的には“イチョウ門”という独立系統
-
狭義の針葉樹ではないが、広葉樹でもない
というのが正確な立ち位置です。
イチョウの形態的特異性
さらに掘り下げると、イチョウの葉は他のどの植物とも異なる特徴を持ちます。
-
葉脈は二又分岐型(forked venation)
-
雌雄異株で、受粉後に種子(ギンナン)を形成
-
葉は落葉性だが、裸子植物で落葉性は少数派
また、精子は鞭毛を持って自力で泳ぐという極めて原始的な性質を保持しており、これはソテツ類と共通する裸子植物の古い特徴です。
まとめ:イチョウは“どちらにも属さない特別な存在”
イチョウは針葉樹でも広葉樹でもない。
分類学的にはそう言うのが最も正確です。イチョウは他の植物とは系統的にも形態的にも一線を画した、まさに「孤高の植物」。そのユニークさゆえに、現代でも多くの研究対象となり、進化の鍵を握る存在として注目されています。
関連する学術用語
-
裸子植物(Gymnosperm)
-
イチョウ門(Ginkgophyta)
-
雌雄異株(Dioecious)
-
鞭毛性精子(Motile sperm)
-
二又分岐葉脈(Dichotomous venation)
丸晴の木に関する動画はこちら